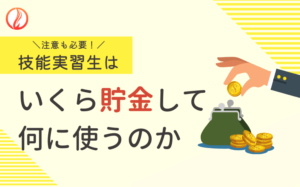技能実習生と万引き
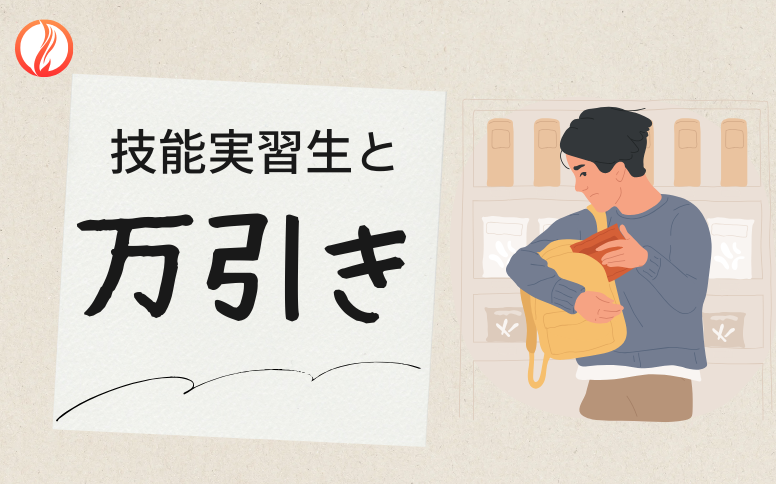
はじめに
技能実習生が日本で働く中で、時折ニュースで万引きの問題が取り上げられることがあります。このような犯罪行為は、単に法律違反であるだけでなく、実習生本人や企業、地域社会にとっても大きな影響を及ぼします。なぜ技能実習生は万引きをしてしまうのか?その背景を掘り下げ、企業や監理団体が取るべき対策について考えてみましょう。
技能実習生の万引き問題の現状
万引き事件に関するデータ
- 外国人による刑法犯罪の割合
- 犯罪白書によると、2022年における、日本での外国人による刑法犯検挙数は1万2,947件(前年比7.9%減)であり、その中でも万引きなどの窃盗犯罪が大きな割合を占めています。
- 窃盗に関しては、ベトナムが2,620件(検挙人員770人)と最も多く、次に中国1,068件(同468人)、ブラジル233件(同123人)という傾向がありました。
- 外国人犯罪率 vs 日本人犯罪率:
- 警視庁によると、2022年のデータでは、日本国内での全体の刑法犯検挙数は 25万350件 でした。
- 外国人による犯罪の割合は全体の 約5% であり、日本人による犯罪が圧倒的に多いことがわかります。
ベトナム人の割合が高くなっている要因
- 技能実習生の母数が多い
- 日本での技能実習生全体の約 半数 がベトナム出身者であり、2022年時点で約 20万人以上 が在籍。そのため、単純に犯罪件数も高くなる傾向がある。
- 経済的困窮
- ベトナムでは、日本への技能実習生として渡航する際に、周辺国で最も多額の仲介手数料を支払うケースが多く、借金を抱えて来日する実習生が多い。
- 家族への送金や生活費の負担が大きく、一時的な困窮により窃盗に手を出すケースが見られる。
- 文化的な違いとルールの認識不足
- 母国では比較的軽視されがちな軽犯罪が、日本では厳しく罰せられることを理解していない場合がある。
- 「少しぐらいなら大丈夫」という誤解が発生しやすい。
- 犯罪組織の影響
- 一部の実習生が犯罪グループに勧誘され、万引きを行い、それを転売するケースも報告されている。
- 「ベトナム人コミュニティ内での組織犯罪」が指摘されており、個人の単独犯だけでなく、複数人で組織的に行動するケースも増えている。
実際の事例
事例1: 衣服類の万引き
- 概要
- Aさんは衣料品店〇〇にてセーター等およそ10点(合計1万円相当)を会計せずにカバンに入れ、店を出た際に防犯ブザーが作動し、店員に制止されました。
- その後、警察が駆けつけ、アプリの通訳を介して事情聴取を受けた後、商品代金を支払い警察署へ連行されました。
- 動機
- 犯行の動機は「計画的ではなく、仕事のストレスで気持ちが沈み、衝動的にやってしまった」と説明。
- 結果
- 指紋採取後、警察の確認が終了し、Aさんは帰宅を許されました。
- 今後、衣料品店〇〇には出入り禁止となりました。
- 本人の意思により母国へ帰国することになりました。
この事例は、技能実習生がストレス環境下でどのような心理状態に陥るのかを示しており、企業や監理団体が適切なメンタルケアを提供する重要性を浮き彫りにしています。
事例2: 万引きの疑いによる警察対応
- 概要
- Bさんはスーパー〇〇で初めて買い物をしました。
- 支払いが現金のみであることを知らず、レジで〇〇カードを提示しましたが決済できませんでした。
- 店の前にある〇〇銀行のATMで〇〇カードへのチャージができるか試そうと、ロピアの店外に出ました。
- その際、未会計の商品(食品3点・2,000円相当)を買い物カゴに入れたまま持ち出してしまい、店舗スタッフに止められ、万引きの疑いで警察に通報されました。
- 動機
- Bさんは、意図的に万引きをしようとしたわけではなく、「〇〇カードのにチャージして会計しよう」と考えていました。
- しかし、未会計の商品を持ったまま店舗を出たことで、意図せず犯罪と疑われる状況になってしまいました。
- また、スタッフに説明しようとしたものの、日本語がうまく伝わらず、結果的に警察の介入を招いてしまいました。
- 結果
- 数時間にわたり警察からの事情聴取を受けた結果、悪質な意図はなく、犯罪ではないと判断され、解放されました。
- Bさんは今回の件に大きなショックを受け、翌日は休みを希望しました。
この事例は、文化の違いや言葉の壁が思わぬトラブルを招くことを示しており、技能実習生がよりスムーズに日本の生活やルールに適応できるよう、企業側のサポートが求められることを示しています。
企業と監理団体が取るべき予防策
1. ルール教育の徹底
- 日本の法律の重要性を説明
- 万引きがどれだけ重い犯罪かを具体的に伝え、軽い気持ちでは済まされないことを自覚させる。
- 文化の違いを理解させる
- 母国との違いを丁寧に教える。場合によってはトラブル事例集等のルールブックを作成し参考にさせる。
2. メンタルヘルスケアの提供
- 相談窓口の設置
- ストレスや不安を気軽に話せる窓口を用意。
- カウンセリング体制
- 定期的に精神的なサポートを提供。
まとめ
技能実習生が万引きをしてしまう背景には、経済的困窮や文化の違い、ストレスなど複数の要因が絡んでいます。これを防ぐためには、企業や監理団体が実習生を経済的・精神的にサポートし、万引きの原因を根本から解決する取り組みが求められます。
実習生が安心して働き、日本社会に貢献できるような環境を整えることが重要です。これには、適切な教育や生活支援、コミュニティ形成が欠かせません。